
投稿日:2025.08.28 最終更新日:2025.09.04
解体工事の車両保険|現場の事故は対象外!プロが教える正しい保険の選び方

解体工事の現場では、日常的に高額な重機や車両を使うため、事故や破損のリスクは常につきまといます。
「うちは車両保険をかけているから安心だ」と思っていても、本当にそれで十分でしょうか?
実は、自動車保険の車両保険はあくまで「公道での走行」を前提とした補償であり、現場特有のリスクにはほとんど対応できません。
ナンバーの付いていない重機や、作業中の破損・盗難といったケースは、車両保険の対象外となるのです。
この記事では、解体業者の皆さまが本当に備えるべき車両リスクに焦点を当て、事業を守るための正しい保険の知識を解説します。
- なぜ自動車保険の車両保険では不十分なのか
- 解体業者が本当に選ぶべき「動産総合保険」とは何か
- 保険料を抑える3つのコツ
- 加入前に必ず確認すべき4つのチェックポイント
なお、解体工事の保険全体を網羅的に理解したい方は、まず以下の記事で全体像を把握いただくと、よりスムーズに読み進められます。

解体工事の保険は「見直し」で大きく変わる!保険料節約と補償を手厚くする方法
解体工事は、数ある建設工事の中でも、特に事故のリスクが高いと言われています。 建物を取り壊していくという作業には、どうしても予測しきれない危うさや、隣接する建物への影響なども考えなくてはいけないからです。 そんな解体工事を営む経営者の方や、現場の安全管理を担う責任者の皆様は、 「うちの会社の保
目次
【結論】自動車保険の車両保険では解体工事のリスクに対応できない

冒頭でお伝えしたように、「すべての車両に保険をかけているから大丈夫」という考えは、解体工事の現場では通用しません。
なぜなら、一般的な自動車保険(車両保険)は、解体工事で本当に備えるべきリスクに対応していないからです。
その理由を、2つのポイントに絞って解説します。
理由1:補償範囲が「公道走行中」に限定されるため
自動車保険は、その名の通り「自動車」が「公道」を走行する際のリスクに備えるための保険です。
そのため、補償の中心は交通事故。 たとえば、交差点での衝突や、走行中のガードレールへの接触といったケースを想定しています。
工事現場という「私有地」での作業中の事故は、たとえナンバープレートが付いている車両であっても、この「公道での走行」という基本ルールから外れるため、補償の対象外となるのが一般的です。
理由2:工事現場特有の「作業リスク」は対象外のため
自動車保険が公道での走行を前提としているのに対し、解体工事の現場では特有の「作業リスク」が数多く存在します。
- 不整地での作業による転倒
- 解体物との接触による破損
- クレーン作業中のバランス崩壊
これらは公道走行では起こりえない事故であり、自動車保険はこうした作業中のトラブルによる損害を補償する設計にはなっていません。
さらに、車両保険の対象となるのは、原則として車検証があり、ナンバープレートが交付されている「登録車両」に限られます。
解体工事で主力となる油圧ショベルやクローラークレーンといったキャタピラで動く重機の多くは、公道を走行しないため登録されていません。 当然、これらは車両保険の対象にはなりません。
つまり、日頃から使っている自動車保険は、解体工事の現場ではほとんど役に立たないのです。
解体工事の車両保険におすすめの「動産総合保険」とは

では、自動車保険が使えないのなら、何で備えればよいのでしょうか。 その答えが、動産総合保険です。
動産総合保険は、事業で使う動産(機械、設備、商品など)の偶発的な事故による損害を広く補償する保険です。
ナンバーの有無にかかわらず、解体工事で使う重機や車両の損害に備えるには、もっとも適した保険といえます。
「動産総合保険」とは?
動産総合保険は、事業で使うための「動産」を広くカバーする保険です。
動産とは、簡単にいえば「動かせる財産」のこと。 解体業者にとっては、油圧ショベルやアタッチメント、ダンプカーなどがこれにあたります。
この保険の大きな特徴は、ナンバーの有無に関係なく、会社の資産である機械類をまとめて補償できる点です。
火災や盗難、輸送中の事故、作業中の操作ミスによる破損まで、さまざまなリスクに一つの保険で備えられます。
「建設工事保険」との違い
ここで、「建設工事保険ではダメなのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。
建設工事保険は、主に新築やリフォーム工事中に、その「工事の対象物(=作っている建物)」や資材の損害に備えるための保険です。
解体工事は「建物を取り壊す」作業であり、リスクの種類や度合いが大きく異なるため、建設工事保険の対象外となるのが一般的です。
高価な機械をさまざまな現場へ移動させながら事業を行う解体業者にとって、その機械自体を守る「動産総合保険」こそが、実態に合った保険といえます。
動産総合保険と自動車保険の違い|解体工事のリスクをカバーする補償内容

動産総合保険は、自動車保険と具体的に何が違うのでしょうか。
主な違いは、以下の3つのポイントに集約されます。
| 比較項目 | 自動車保険(車両保険) | 動産総合保険 |
|---|---|---|
| 対象範囲 | ナンバープレート付きの登録車両 | ナンバーの有無を問わない事業用の動産(重機、アタッチメント、工具など) |
| 補償場面 | 主に「公道での走行中」 | 「作業中」「保管中」「輸送中」など事業活動のあらゆる場面 |
| 補償内容 | 交通事故による自車の修理費が中心 | 火災、盗難、破損、輸送中の事故など、より広範なリスクに対応 |
対象範囲の違い:アタッチメントや工具類もカバー
自動車保険がナンバー付きの車両しか対象にできないのに対し、動産総合保険は、事業で使う機械類を広くカバーできます。
例えば、油圧ショベルの先端に装着するアタッチメント(破砕機やカッターなど)や、現場で使う発電機、工具類なども保険の対象に含められます。
補償場面の違い:作業中から輸送中まで
補償される場面も大きく異なります。
自動車保険が「公道での走行中」に限定される一方、動産総合保険は「会社の敷地での保管中」「現場への輸送中」「現場での作業中」と、事業活動のあらゆる場面をカバーします。
まさに、解体業者向けの保険といえるでしょう。
補償内容の違い:盗難や操作ミスによる破損も
動産総合保険は、交通事故だけでなく、より幅広いリスクに備えられます。
- 火災・落雷・風災:保管場所での火災や、台風による損害
- 盗難:現場や資材置き場からの重機・車両の盗難
- 輸送中の事故:現場への搬入中に、荷台から重機が落下し破損した
- 作業中の破損:操作ミスで重機のアームを曲げてしまった
このように、自動車保険では対応できない、現場特有のさまざまなリスクをカバーできるのが、動産総合保険の大きな強みです。
ただし、機械の経年劣化による故障や、故意・重大な過失による損害は対象外となるので注意しましょう。
ケース別の適用早見表と事例
ここでは実際にあった事故事例を3つのパターンに分けて見ていきましょう。
パターン1:重機そのものが壊れるリスク(→動産総合保険)

まずは、重機そのものが壊れてしまうケースです。
リース重機の操作ミスによる破損
基礎解体工事で借りていた重機を操作中にアーム部分を破損。リース会社から137万円を超える修理費用を請求された。
こうした「自社やリース会社の所有する車両・重機そのもの」の損害に備えるのが、この記事のテーマである動産総合保険です。
パターン2:第三者のモノを壊してしまうリスク(→賠償責任保険)

次に、自社の重機が原因で、第三者のモノを壊してしまうケースを見てみましょう。
隣接する駐車場の破損
重機が隣のコインパーキングに入り、アスファルトを破損。補修費用として約28万円を賠償した。
他社の車両との接触
現場で作業中の重機が、他業者の生コン車に接触し損傷させた。賠償金として約15万円を支払った。
公共物の破損
ビル解体工事の際、重機が境界ブロックに衝突して道路施設を破損。112万円を超える賠償責任を負った。
このような「第三者の身体や財産」への損害に備えるのが賠償責任保険です。この記事で扱う動産総合保険とは役割が異なる、もう一つの重要な保険です。
パターン3:公道上での車両トラブル(→自動車保険)

最後に、現場ではなく公道で起こるトラブルのケースです。
業務車両の故障
従業員が運転する業務車両が公道で故障し、走行不能に。レッカーで搬送し、費用として約15万円が発生した。
こうした「公道走行中」のトラブルに備えるのが、皆さんがよくご存知の自動車保険です。
解体工事の車両保険料を抑える3つの方法

動産総合保険の必要性はわかったけれど、やはり気になるのが保険料。
少しでもコストは抑えたい、というのが本音でしょう。
保険料は、補償する機械の価値や業種、過去の事故歴などによって決まりますが、以下の3つの工夫で負担を軽くできます。
- 補償範囲を適正化する
- 免責金額を調整する
- 団体割引を活用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
補償範囲を適正化して保険料を抑える
「あれもこれも」と心配して手厚い補償を付ければ、当然、保険料は高くなります。
自社の状況に合わせて、本当に必要な補償を見極めることが大切です。
例えば、会社の所在地や主な現場が高台にあり、河川からも遠いなど、水害のリスクが極めて低い場合。
この場合、「水災補償」を対象外とすることで、そのぶん保険料を安くできる可能性があります。
ただし、こうした判断には専門的な知識が必要です。 自己判断で安易に補償を外すのではなく、必ず保険の専門家に相談し、リスクを評価したうえで決定しましょう。
免責金額を調整して保険料を最適化
免責金額とは、万が一の事故の際に、自己負担する金額のことです。
例えば、免責金額を20万円に設定している場合、100万円の修理費用がかかる事故が起きても、保険会社から支払われるのは80万円となります。
この免責金額を高く設定すればするほど、保険会社の負担リスクが減るため、支払う保険料は安くなります。
「この金額までの損害なら、保険を使わずに自社で対応できる」というラインを、会社の財務状況に合わせて見極めることが重要です。
小さな損害は自社でカバーし、保険はあくまで「経営を揺るがす大きな損害」に備える、と割り切るのも一つの考え方です。
団体割引を活用してコストを削減
建設業協会や商工会議所といった事業団体の中には、会員企業向けに割安な団体保険制度を用意しているところがあります。
同じ補償内容であっても、個人で契約するより保険料が安くなるケースが多いため、自社が所属している団体にそうした制度がないか、一度確認してみることをおすすめします。
私たち株式会社マルエイソリューションでも、独自の団体割引制度「マルエイ取引先協力会」をご用意しており、実際に、こうしたプランの総合的な見直しによって、年間の保険料を約80%も削減できた事例もあります。 (引用:マルエイソリューション)
こうした制度をうまく活用することも、コスト削減の有効な手段です。

解体工事の保険は「見直し」で大きく変わる!保険料節約と補償を手厚くする方法
解体工事は、数ある建設工事の中でも、特に事故のリスクが高いと言われています。 建物を取り壊していくという作業には、どうしても予測しきれない危うさや、隣接する建物への影響なども考えなくてはいけないからです。 そんな解体工事を営む経営者の方や、現場の安全管理を担う責任者の皆様は、 「うちの会社の保
解体工事の車両保険加入前に確認すべき4つのポイント
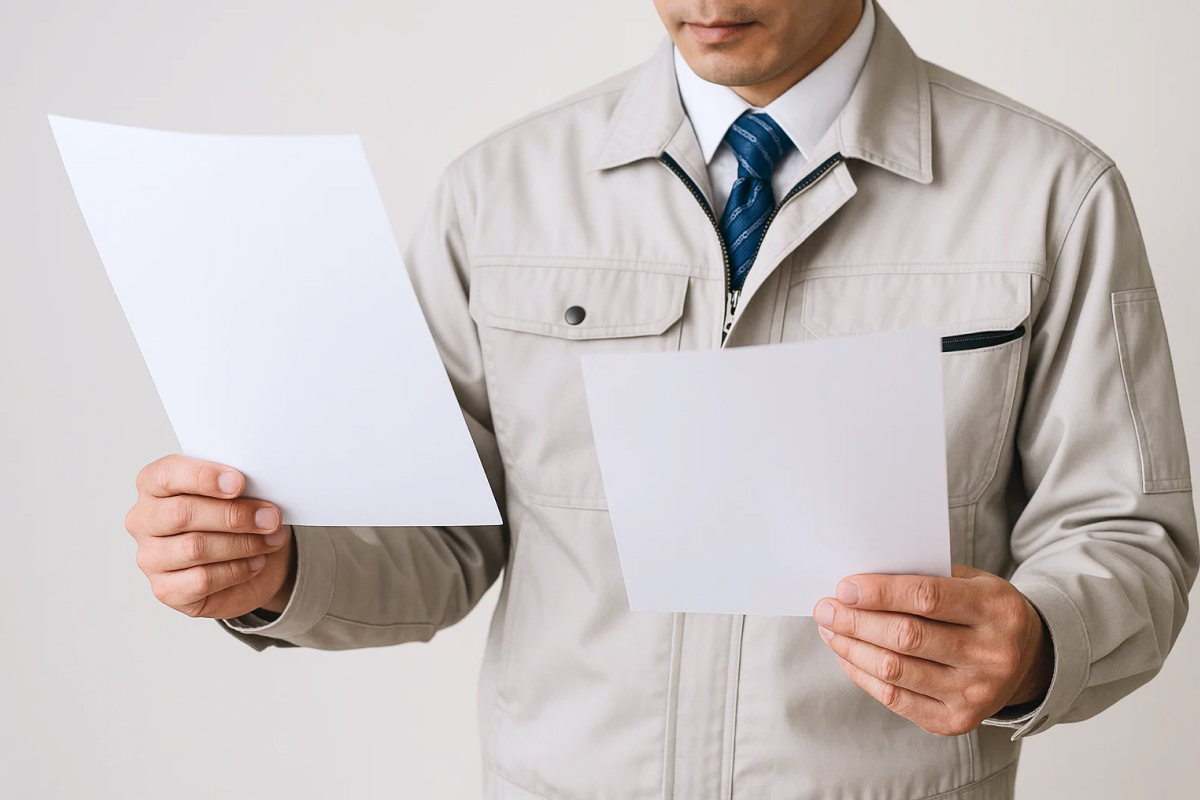
最後に、実際に動産総合保険に加入したり、今入っている保険を見直したりする際に、失敗しないためのポイントを確認しましょう。 この機会に、自社の保険が万全か、ぜひ確認してみてください。
特に重要なチェックポイントは、以下の4つです。
- 保険の対象リストは最新か
- リース重機の補償は十分か
- 他の保険との重複や漏れはないか
- 事故時の対応フローは明確か
一つずつ見ていきましょう。
保険の対象とする機械・設備のリストは最新か
保険を契約する際には、対象となる機械や設備の一覧(保険の対象明細)を保険会社に提出します。
このリストが古いままになっていると、新しく購入した重機が保険の対象から漏れていた、という事態になりかねません。
高価な機械を買い替えた際や、新たな設備を導入した際には、都度、保険代理店に連絡し、リストを最新の状態に保つことを心がけましょう。
リース契約の重機は補償範囲に含まれているか
リースやレンタルで重機を借りる場合、その保険関係は特に注意が必要です。
「リース会社が保険に入っているから大丈夫」とは限りません。
リース会社がかけている保険は、多くの場合、リース会社自身の資産を守るためのものであり、借りている側の操作ミスによる破損まではカバーしていないケースがほとんどです。
まずはリース契約書をよく確認し、万が一、自社の責任で壊してしまった場合にどうなるのか、保険の責任範囲を明確に把握しましょう。
もし補償が不十分であれば、自社で動産総合保険をかけるか、「受託物賠償責任特約」といったオプションを検討する必要があります。

重機の事故・盗難は保険で守る!リースの注意点や30%のコスト削減方法も解説
建設現場に欠かせない大型重機。高価な機械であると同時に、操作を誤れば大きな事故につながる危険性もはらんでいます。 横転や接触といった操作ミスによる事故はもちろん、近年は盗難被害も後を絶たず、頭を悩ませている事業者の方も多いのではないでしょうか。 ひとたびトラブルが発生すれば、多額の修理費や賠償金
他の保険との補償の重複や漏れはないか
会社で加入している保険は、動産総合保険だけではないはずです。 例えば、第三者への損害に備える「賠償責任保険」など、他の保険との関係を整理することも大切です。
- 重機をぶつけて隣の家の壁を壊した→賠償責任保険
- 操作ミスで重機自体が壊れた→動産総合保険
このように、それぞれの保険が担う役割は異なります。
自社のリスク全体を洗い出し、補償に漏れがないか、あるいは重複して無駄な保険料を払っていないか、専門家と一緒に確認することをおすすめします。
事故時の連絡体制と手続きは明確か
いざ事故が起きてしまった時に、慌てずスムーズに対応できるかどうかも重要なポイントです。
事故発生後に保険会社への連絡が遅れると、「通知義務違反」と見なされ、保険金が減額されたり、支払われなかったりするケースもあります。
- 誰が、どこに、いつまでに連絡するのか
- どのような書類や写真が必要になるのか
といった事故後の流れを事前に確認し、社内で共有しておきましょう。
事故時の連絡先を重機の運転席に貼っておく、といった簡単な工夫も有効です。
まとめ:解体工事の車両保険は、自動車保険ではなく動産総合保険!コストと合わせて見直しを!
ここまで、解体工事における車両・重機のリスクと、それに対応する保険について解説してきました。
自動車保険だけでは不十分であり、事業の実態に合った「動産総合保険」で備えることの重要性をご理解いただけたかと思います。
- 自動車保険では不十分:公道での走行が前提のため、現場のリスクは対象外。
- 動産総合保険が最適:ナンバーを問わず、作業中や盗難など現場のリスクを広くカバー。
- 保険料を抑えるコツ:補償内容の見直し、免責金額の調整、他の保険との重複整理がカギ。
- 保険選びの要点:対象範囲、補償内容、保険金額、免責金額、代理店の専門性を必ず確認。
「今の保険内容で十分か不安」
「もっと保険料を安くしつつ、必要な補償を確保できないか?」
もしそうお考えなら、一度、私たち株式会社マルエイソリューションにご相談ください。
私たちは、解体業をはじめとする建設業の保険を専門にあつかうプロフェッショナルです。
- コスト削減に自信あり!
独自の団体割引(入会費・年会費無料の「マルエイ取引先協力会」など)や、保険会社ごとのプラン比較により、保険料の大幅な削減を目指せます。 - 豊富な選択肢から最適プランをご提案
国内外の主要保険会社・40以上の商品の中から、お客様の重機の種類や使用状況、リース契約の有無などを踏まえ、過不足のない最適な補償プランを公平な視点で厳選します。 - 安心の実績とサポート
これまで多くのお客様の保険選びをお手伝いし、継続率95%以上という高いご支持をいただいています。
コストの削減と、事業の安心の両立を全力でサポートします。
ご相談やお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。




