
投稿日:2025.08.29 最終更新日:2025.08.29
解体工事の保険|賠償責任はどこまで?コストと補償の最適解を保険のプロが解説
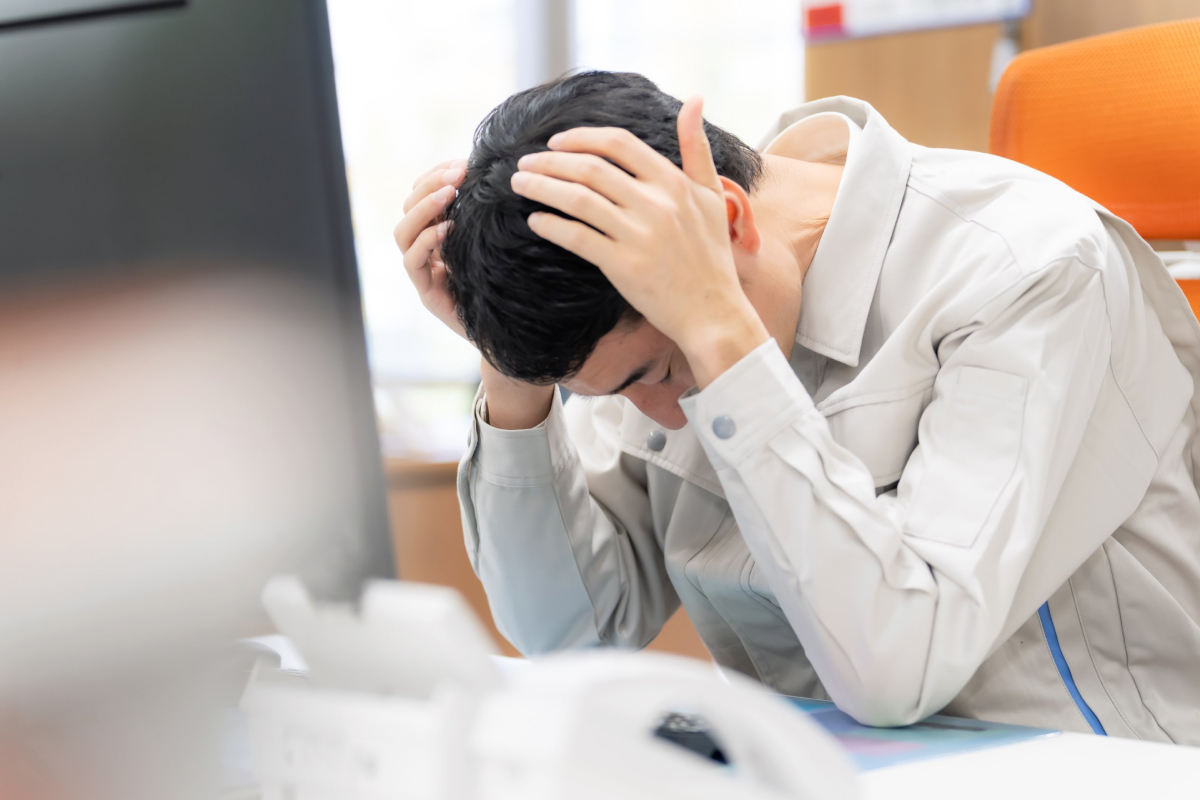
解体工事の現場は、一見すると単なる建物の取り壊し作業に思えますが、その裏には数千万円から1億円を超えることもある高額な賠償責任リスクが潜んでいます。
重機やクレーンの事故、粉じんやアスベストの飛散、騒音や振動による近隣トラブル
──これらは決して珍しいケースではなく、どの解体業者にも起こりうる身近なリスクです。
こうした万が一に備えるために欠かせないのが、解体工事の「賠償責任保険」。
しかし、ひとくちに保険といっても、補償される範囲とそうでない範囲があったり、保険料や特約の内容もさまざまだったりと、その仕組みは意外と複雑です。
この記事では、解体工事で実際に起こりうる賠償リスクの事例から、保険の仕組み、そしてコストを上手に抑えるためのポイントまで、分かりやすく解説していきます。
「もしもの事故から、どうやって会社を守るか」という視点で、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
- 解体工事に潜む具体的なリスクと賠償事例
- 事故の際の法的責任と、保険がどこまでカバーしてくれるのか
- 保険料を抑えつつ、必要な補償を確保するための方法
- 万が一の事故でも慌てない、保険金請求の流れとコツ
- 自社にぴったりの保険を提案してくれる代理店の見つけ方
目次
解体工事に潜む賠償責任リスクとは?7種類の事故事例
解体工事の現場には、常にさまざまな危険が潜んでいます。
ここでは、実際に起こりがちな7つの事故事例をもとに、どのような賠償責任が発生する可能性があるのかを具体的に見ていきましょう。
【事例1】重機・クレーンの転倒や部材落下による第三者への被害

解体現場でよく起こる事故の一つが、重機やクレーンが関わるトラブルです。
たとえば、作業中のクレーン車がバランスを崩して倒れ、隣のビルや住宅を壊してしまうケース。
また、高い場所での作業中に工具や解体した部材が落ちてしまい、通行人や駐車中の車に被害を与えてしまう事故も少なくありません。
こうした「重機の転倒」や「つり荷の落下」は、代表的な対物・対人事故といえます。
壊してしまった建物や車の修理費用(対物賠償)はもちろん、もし通行人にけがをさせてしまった場合は、治療費や休業補償、慰謝料(対人賠償)の支払いが必要になります。
特に人が関わる事故の場合、賠償額は数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。
【事例2】粉じん・アスベストの飛散による近隣への健康被害

解体作業で発生する粉じんや、より深刻なアスベスト(石綿)の飛散は、周辺の環境に大きな影響を与えかねないリスクです。
粉じんが風で広がり、近所の家の壁や車を汚してしまうといった物的な被害。
さらに、アスベストが飛散した場合は、周辺住民に健康被害をもたらすという、より大きな問題に発展する恐れもあります。
ここで注意したいのが、多くの賠償責任保険では、こうした公害のような性質の損害は、補償の対象外(免責)とされている点です。
この種のリスクに備えるには、通常の保険とは別に、専門の保険や特約への加入が必須となります。
粉じんの場合は、近所の家や車の洗浄費用が主な賠償内容です。
しかし、アスベストを飛散させてしまったとなると話は別で、周辺住民の健康に長く影響を及ぼすため、治療費や高額な慰謝料、定期的な健康診断の費用など、長期間にわたる高額な賠償責任を負う可能性があります。
【事例3】騒音・振動が原因の近隣トラブル

解体工事に騒音や振動はつきものですが、これがもとで近隣とのトラブルに発展するケースは少なくありません。
工事の振動で隣の家の壁にひびが入ってしまった、といった物理的な損害はもちろん、「工事の音がうるさくて眠れない」といった健康上の問題を理由に、慰謝料を請求されることもあります。
保険の話でいうと、騒音や振動は「工事に通常ともなうもの」と見なされるため、基本的には補償の対象外です。
ただし、振動が原因で壁に亀裂が入るなど、はっきりとした物理的な損害が出た場合には、「結果的に生じた対物事故」として保険でカバーされることもあります。
振動で隣家の壁にひびが入った場合は、その補修費用が賠償の対象です。
また、騒音が原因で近隣住民が不眠などの健康被害を訴え、その因果関係が認められた場合には、慰謝料の支払いが必要になることもあります。
【事例4】解体材の飛散による近隣家屋や車両の損壊

この事例のように、解体作業中にはコンクリート片や木材といった解体材が思わぬ方向へ飛んでいき、近隣に被害を与えてしまうことがあります。
これは、私たちが扱う事故の中でもとくに多いケースです。
飛んでいった解体材が隣の家の窓ガラスを割ってしまったり、駐車してあった車をへこませてしまったり、といった物損事故は決して珍しいことではありません。
たとえ養生シートをしっかり設置していても、その隙間から小さな破片が漏れ出ることもあり、飛散を100%防ぐのは非常に難しいのが現実です。
窓ガラスの修理費用や、車の板金塗装費用などが具体的な賠償内容になります。
被害の程度や対象物によって金額は変わりますが、高級車や特殊な建材が使われている建物だった場合、思った以上に高額な賠償になることもあります。
【事例5】地中埋設物やライフラインの破損事故

地面の下に隠れている「地中埋設物」や、私たちの生活を支える「ライフライン」を壊してしまうと、大きな問題に発展します。
たとえば、重機で地面を掘っているときに、誤って地中のガス管や水道管を破損させてしまうような事故です。
ライフラインを止めてしまえば、広い範囲で供給がストップし、社会的な影響も大きくなります。
保険の観点から見ると、第三者が所有するライフラインを壊した場合は、基本的には「請負業者賠償責任保険」で補償されます。
しかし、多くの保険契約では「地中にあるもの」への損害は標準で補償対象外になっているため、「地中埋設物損壊補償特約」を付けておかないと、いざというときに保険金が支払われない可能性が高いので注意が必要です。
ガス管や水道管そのものの修理費用に加えて、供給が止まったことで影響を受けた近隣への賠償も発生します。
例えば、飲食店が営業できなくなった場合の休業補償など、二次的な被害に対する賠償責任も問われる可能性があります。
【事例6】作業員の過失を原因とする火災・延焼

解体現場は、常に火災のリスクと隣り合わせです。
とくに木造家屋の解体では、金属をガスで切断するときの火花が燃え移ったり、作業員のたばこの不始末といったささいな不注意が、大きな火事につながる危険があります。
ひとたび火災が起きれば、解体中の建物だけでなく、隣の住宅にまで燃え広がる「延焼」のリスクも考えなくてはなりません。
もし延焼で他人の財産に損害を与えてしまえば、その賠償責任は計り知れないものになります。
隣の家を延焼させてしまった場合、その建物の価値や家財道具、焼け跡の片付け費用など、損害のすべてを賠償する責任を負うことになります。
被害が何軒にも及べば、賠償額は非常に大きな金額になる場合があります。
【事例7】第三者の敷地への無断侵入とそれに伴うトラブル

解体工事では、作業スペースを確保するために、お隣の敷地を一時的にお借りすることがあります。
しかし、その際に所有者の許可を得ていなかったり、約束の範囲を超えて使ってしまったりすると、思わぬトラブルになることがあります。
たとえば、「隣の家の庭に無断で立ち入って作業し、庭木を傷つけてしまった」といったケースです。
これらは不法行為と見なされ、損害賠償を請求される原因になります。
傷つけてしまった庭木や塀などの修理・元通りにするための費用が賠償の対象です。また、無断で立ち入ったこと自体に対して、慰謝料を請求されることも考えられます。
これらは決して特別なケースではありません。どの現場にも潜んでいる現実的なリスクであり、ひとたび起きてしまえば、会社の経営を揺るがしかねない高額な賠償責任につながる可能性があるのです。
解体現場での事故の責任は誰が負う?法律上のルールと事業者の責任

万が一、解体工事で事故が起きてしまった場合、その責任は一体誰が、どのように負うことになるのでしょうか。
基本は元請け業者の「使用者責任」(民法715条)
事故の責任を考えるうえで基本となるのが、民法715条で定められた「使用者責任」という考え方です。
これは、従業員が仕事中に第三者へ損害を与えてしまった場合、その従業員を雇っている会社も一緒に賠償責任を負わなければならない、というルールです。
つまり、実際に事故を起こしたのが現場の作業員であっても、被害を受けた方はその作業員個人だけでなく、雇い主である解体業者(会社)に対しても「損害を賠償してください」と請求できるわけです。
この「使用者責任」という考え方は、下請け業者が起こした事故についても元請け業者の責任が問われる可能性がある、という点でも知っておく必要があります。
「作業は下請けに任せていたから関係ない」という言い分は、法律の世界では通用しません。
【例外】発注者(施主)に責任が及ぶケース
では、工事を依頼した施主(お客様)にまで責任が及ぶことはないのでしょうか。
これについては、民法716条の「注文者の責任」でルールが決められており、基本的には、施主が解体業者の起こした事故の賠償責任を負うことはありません。
ただし、例外もあります。
それは、「注文や指示の仕方に、注文者の側にも落ち度があったとき」です。
たとえば、施主が無理なスケジュールや危険な作業方法を強く求め、その結果として事故が起きたようなケースでは、施主にも責任の一部があると判断される可能性があります。
損害賠償額は数千万円を超えることも
解体工事の事故で発生する賠償金の額は、決して甘く見てはいけません。
建物や車を壊してしまったといった物損事故であれば、数十万円から数百万円で済むこともありますが、人が関わる人身事故になると、賠償額は一気に跳ね上がります。
もし作業中の落下物が通行人に当たってしまい、後遺症が残るような大怪我をさせてしまったり、最悪の事態として亡くならせてしまったりした場合には、1億円近い賠償金の支払いが命じられた過去の判例もあります。
もし保険に入っていなければ、こうした高額な賠償金が会社の経営に重くのしかかり、事業を続けること自体が難しくなってしまう可能性もゼロではないのです。
解体業者が入っておくべき保険の種類と基本的な補償内容

こうした大きな賠償リスクから会社を守るために不可欠なのが、賠償責任保険です。
ここでは、解体業者が入っておくべき保険のメインとなる「請負業者賠償責任保険」を中心に、どんな種類があって、何を補償してくれるのか、そして意外と知られていない「保険金が支払われないケース」について解説していきます。
中心となるのは「請負業者賠償責任保険」
解体業者にとって、もっとも基本となる重要な保険が「請負業者賠償責任保険」です。
これは、解体工事の作業中に、偶然の事故で第三者の身体や財産に損害を与えてしまい、法律上の賠償責任を負うことになった場合に、その損害をカバーしてくれる保険です。
この保険は、大きく分けて2つの補償で成り立っています。
- 対人賠償: 第三者を死傷させてしまった場合の治療費や慰謝料などを補償します。
- 対物賠償: 第三者の「モノ」を壊してしまった場合の修理費用などを補償します。
「請負業者賠償責任保険」に入っておけば、これら対人・対物の両方のリスクに一つの契約でまとめて備えることができるため、まさに解体業者のための「守りの基本となる保険」といえるでしょう。
労災保険・建設工事保険との違い
賠償責任保険とよく混同されがちな保険に、「労災保険」と「建設工事保険」があります。
これらは目的が違うので、その違いを理解し、きちんと使い分けることが大切です。
労災保険(労働者災害補償保険)との違い
これは、自社の従業員や下請けの作業員が、仕事中にケガをした場合などに使われる保険制度です。
賠償責任保険が「他人への損害」に備えるのに対し、労災保険は「自社側の働く人を守る」ことを目的としており、全くの別物と理解しておきましょう。
従業員を一人でも雇っている場合は、加入が法律で義務付けられています。
なお、国が定める労災保険だけでは、慰謝料など、基準を超える部分の補償はカバーされません。
こうした不足分を補って、従業員への補償を手厚くするために任意で加入できる「労災上乗せ保険」というものもありますので、あわせて知っておくとよいでしょう。
建設工事保険との違い
建設工事保険は、工事の対象となっている建物そのものや、現場に置いてある資材・機材などが壊れた場合に、その修理費用などを補償する保険です。
しかし、一般的な建設工事保険では、リスクが高いという理由で、解体工事は補償の対象外となっていることがほとんどです。
解体業者が優先して備えるべきは、やはり第三者への損害に備える「請負業者賠償責任保険」と、自社の従業員を守る「労災保険」ということになります。
【要注意】保険金が支払われない「免責事項」とは?

しかし「保険に入っているからどんな事故でも大丈夫」と考えるのは、少し注意が必要です。
すべての保険契約には、保険金が支払われない特定のケース、つまり「免責事項」が決められています。
解体工事の賠償責任保険で、とくに注意しておきたい代表的な免責事項は、次のようなものです。
- 工事対象物そのものの損壊
- レンタル重機など借りている物の破損
- 騒音・振動・粉じん飛散による被害
- 法律違反が原因の事故
- 地震や噴火、津波といった天災による被害
- アスベストによる被害
これらの免責事項は、保険の契約書(約款)に必ず書かれています。
契約する前はもちろん、今入っている保険についても、一度内容をしっかり確認しておくことが大切です。
アスベストや地中埋設物など特殊リスクへの備え方

解体工事には、アスベストの除去や地中埋設物の撤去といった、とくに専門的な注意が必要な「特殊リスク」がつきものです。
そして、これらのリスクは、基本的な請負業者賠償責任保険では「免責事項」にあたるため、そのままでは補償されないことがほとんどです。
アスベスト飛散リスクへの備え
アスベスト(石綿)を飛散させてしまい、第三者の健康や周りの環境に損害を与えてしまった場合、その賠償責任は非常に重いものになります。
このリスクは通常の賠償責任保険ではまずカバーされないため、専門の保険や特約への加入が実質的に必須です。
地中埋設物破損リスクへの備え
地中から想定外の障害物が見つかり、それを撤去する費用は、誰かに対する賠償ではないため、保険の対象外となります。
保険で備えるべきなのは、その埋設物に気づかずに掘削作業を進めた結果、隣の敷地のガス管や水道管を壊してしまった、といったケースです。
しかし、これも「地中埋設物損壊補償特約」などをつけていなければ補償されません。
これらの特殊リスクをともなう工事を行う可能性がある場合は、必ず保険代理店によく相談し、自社の仕事内容に合った特約をつけるなど、きちんと備えておくことが不可欠です。
解体工事の賠償責任保険料はいくら?相場とコストを抑えるポイント

賠償責任保険の大切さは分かっていても、やはり気になるのは「保険料」ですよね。
ここでは、保険料が決まる仕組みから実際の相場観、そして補償内容は妥協せずにコストを上手に抑えるための具体的な方法まで、分かりやすく解説していきます。
保険料の相場と決まり方
解体工事の賠償責任保険料は、会社の売上規模や工事の内容によって大きく変わり、安い場合は年間5万円くらいから、大きな事業者になると年間数百万円になることもあります。
この保険料は、主に以下の4つの要素で決まります。
- 年間完工高(売上規模)
- 業種(リスクの高さ)
- 補償範囲(補償額や特約)
- 割引率
とくに知っておきたいのは、同じ補償内容でも、保険会社によって保険料が2倍以上違うことも珍しくないという点です。
だからこそ、複数の会社を比較することが、コストを抑えるための重要なポイントになります。
補償を妥協せずに保険料を抑える4つの方法

「手厚い補償」と「コスト削減」は、やり方次第で両立できます。
具体的には、以下の4つの方法が考えられます。
- 複数社から相見積もりを取る
- 安全対策の取り組みを交渉材料にする
- 団体割引制度を活用する
- 補償内容を見直して無駄をなくす
①複数社から相見積もりを取る
もっとも基本的で、かつ効果的な方法が、複数の保険会社から見積もりを取る「相見積もり」です。
一見、手間がかかるように感じるかもしれませんが、この一手間をかけるかどうかで、年間の保険料が大きく変わってきます。
なぜなら、保険料は「どの保険会社も同じ」ではないからです。
保険会社ごとに、得意な業種やリスクの評価の仕方、利益率などが違うため、同じ補償内容でも提示される保険料に何十万円もの差がつくことも決して珍しくありません。
②安全対策の取り組みを交渉材料にする
日頃から安全管理をしっかり行っている会社は、保険会社から「事故リスクの低い、優良な契約者」と見てもらえます。
その取り組みを積極的にアピールすることで、保険料の割引交渉を有利に進められる可能性があります。
たとえば、長年の無事故実績や、従業員向けの定期的な安全教育の実施記録、ヒヤリ-ハット報告の収集と再発防止策といった、安全への具体的な取り組みを資料として示して交渉するのです。
過去に事故がないという実績だけでなく、未来の事故を防ぐための体制が整っていることを示すことで、保険料の割引を引き出しやすくなります。
③団体割引制度を活用する
団体割引とは、建設業協会のような同業者団体が、所属するメンバーのために保険会社とまとめて契約することで、個人で入るよりも割安な保険料が適用される制度です。
多くのメンバーがまとまって加入するため、保険会社としてもリスクを分散でき、結果として個人で契約するより10%〜30%ほど安くなるケースも珍しくありません。
④補償内容を見直して無駄をなくす
長年同じ保険に入り続けていると、事業内容の変化で今では不要になった特約がついたままになっていることがあります。
まずは自社のリスクを改めて見直し、補償内容を整理するだけでも、無駄な保険料をカットできます。
しかし、もっと大きな効果を期待できるのが、保険会社やプランそのものを見直すことです。
同じ補償内容であっても、保険会社が違うだけで年間の保険料が数十万円単位で安くなることも少なくありません。
実際に、私たちマルエイソリューションがお客様の保険全体の見直しをお手伝いした結果、年間の保険料を約80%も削減できたという事例もあります。 (参考:マルエイソリューション)
現在の保険を長く続けている会社様ほど、専門家の視点で見直すことで、大きなコスト削減が期待できるかもしれません。
万が一の事故発生時、保険金請求をスムーズに進めるには?
どれだけ万全の対策をしていても、事故が起きる可能性をゼロにすることはできません。
万が一事故が起きてしまったときに、慌てずに、スムーズに保険金請求の手続きを進めるための流れと、大事なポイントを解説します。
事故発生から保険金支払いまでの流れ

事故が起きてから保険金が支払われるまでの大まかな流れは、次のようになります。
| 事故発生・初動対応 | まずはけがをした人の救護と、これ以上被害が広がらないように安全を確保することを最優先します。 |
|---|---|
| 証拠の保全 | 事故現場の状況を写真や動画でいろいろな角度から撮影し、関係者の連絡先や話した内容を記録しておきます。 |
| 保険会社/代理店へ連絡 | できるだけ早く、保険会社か保険代理店へ事故が起きたことを報告します。 |
| 損害の確認・示談交渉 | 保険会社の担当者が現場の損害状況を確認し、被害者の方と賠償額を決めるための話し合い(示談交渉)を進めます。 |
| 必要書類の提出 | 話し合いがまとまったら、保険会社から求められる書類(事故報告書、修理見積書、示談書など)を提出します。 |
| 保険金の支払い | 書類に問題がなければ、指定の口座に保険金が支払われます。 |
この一連の流れを頭に入れておくことも大切ですが、中でもとくに重要なのが、事故が起きた直後の「初動対応」「証拠の保全」「保険会社への連絡」という最初のステップです。
ここでの対応が、その後の示談交渉や保険金請求がうまくいくかどうかを大きく左右するといえます。
請求をスムーズに進めるための3つのポイント

保険金請求をスムーズに進め、適切な保険金をできるだけ早く受け取るためには、とくに以下の3点が重要です。
- ポイント1:冷静な初動対応と証拠の確保
- ポイント2:迅速で正確な事故報告
- ポイント3:必要書類をもれなく準備
ポイント1:冷静な初動対応と証拠の確保
事故が起きた直後でも慌てず冷静に対応し、客観的な証拠をしっかり残しておくことが何よりも大切です。
壊れた箇所や現場全体の状況を写真に撮っておく、といった行動が、後の示談交渉をスムーズに進めるうえで大きな助けになります。
ポイント2:迅速で正確な事故報告
事故の報告は、記憶がはっきりしているうちに行うのが鉄則です。
「いつ、どこで、誰が、何を、どうした結果、どうなったか」を、自分の憶測などを入れずに、客観的な事実だけを正確に伝えましょう。
ポイント3:必要書類をもれなく準備
保険金の請求には、事故報告書や修理見積書、示談書など、いろいろな書類が必要になります。
保険会社や代理店の指示に従って、漏れや間違いがないようにしっかり準備しましょう。
解体工事の保険は誰に相談すべき?失敗しない代理店の選び方

自社に本当に合った保険プランを見つけ、納得のいく保険料で契約するためには、パートナーとなる保険代理店選びが非常に重要です。
ここでは、信頼できる代理店を見極めるためのポイントと、複数の代理店を比較することのメリットを解説します。
信頼できる代理店を見極める3つのポイント
良い保険代理店を選ぶためには、以下の3つの点を確認してみてください。
- 解体工事業界への専門知識・経験は豊富か
- 事故対応などのサポート体制は万全か
- 複数の保険会社の商品を公平に比較できるか
1. 解体工事業界への専門知識・経験は豊富か
解体工事という特殊な仕事のリスクを深く理解している代理店でなければ、本当に必要な補償を提案することは難しいでしょう。
2. 事故対応などのサポート体制は万全か
保険は、加入時よりも、事故が起きた後の対応こそが本当の価値を問われます。
万が一の際に、すぐに相談に乗ってくれるか、保険金請求の手続きを丁寧に手伝ってくれるかを確認することが大切です。
3. 複数の保険会社の商品を公平に比較できるか
一つの保険会社の商品しか扱えない代理店よりも、複数の保険会社の商品を比較・検討できる「乗合代理店」の方が、より中立的な立場で自社に合ったプランを提案してくれる可能性が高いでしょう。
まとめ:自社の解体工事の賠償責任リスクと保険内容、本当に合っていますか?
この記事では、解体工事にともなう具体的な賠償責任リスクの事例から、備えておくべき保険の基本、そしてコストを抑えるポイントまで解説してきました。
重機による事故やアスベストの飛散、あるいは地中埋設物の破損といったリスクは、決して他人事ではありません。
そして、基本的な賠償責任保険だけでは、これらの特殊なリスクに対応できないケースがあることもお伝えしました。
- リスクの再認識: 重機事故や近隣トラブルなど多様な賠償責任リスク。
- 保険の要点: 基本は「請負業者賠償責任保険」。特約や免責事項の確認も忘れずに。
- コスト削減: 団体割引の活用、補償内容の見直しで、保険料は削減可能。
- 代理店選び: 業界知識とサポート体制が充実したパートナーを選ぶ。
「今の保険で、本当に自社のリスクをすべてカバーできているだろうか?」 「もっと保険料を抑えつつ、必要な補償を手厚くする方法はないだろうか?」
もし少しでもこう感じたなら、それは保険を見直す良い機会かもしれません。
私たちマルエイソリューションは、国内外の主要保険会社の商品を比較し、お客様一社一社の状況に合わせた最適なプランをご提案する工事保険のプロフェッショナルです。
- コスト削減に自信あり!
独自の団体割引(入会費・年会費無料の「マルエイ取引先協力会」など)や、保険会社ごとのプラン比較により、保険料の大幅な削減を目指せます。 - 豊富な選択肢から最適プランをご提案
国内外の主要保険会社・40以上の商品の中から、お客様の重機の種類や使用状況、リース契約の有無などを踏まえ、過不足のない最適な補償プランを公平な視点で厳選します。 - 安心の実績とサポート
これまで多くのお客様の保険選びをお手伝いし、継続率95%以上という高いご支持をいただいています。
貴社のリスクに本当に見合った保険なのか、ぜひ一度、私たちと一緒に確認してみませんか。
これまでの実績と専門知識をもとに、コストと補償のバランスが取れた、納得のいくプランをご提案します。





