
解体工事のアスベスト保険|補償範囲と注意点【2025年最新版】

解体工事におけるアスベスト対策について、「うちの会社は、ちゃんと工事保険に入っているから大丈夫」とお考えの場合は、一度お手元の保険証券を確認してみてください。
その保険証券の小さな文字で書かれた部分に、「アスベスト(石綿)による損害は補償の対象外」という一文が見つかるかもしれません。
実は、多くの事業者が加入されている一般的な工事保険では、アスベストが原因の事故は補償の対象外となっていることがほとんどなのです。
もし、アスベストによる健康被害や飛散事故が起きてしまうと、損害賠償額が数千万円から億単位にのぼるケースも考えられます。
この記事では、解体工事のアスベストリスクに必要な保険の種類、補償範囲、そして2025年時点の最新法規制を専門家の視点で解説します。
- アスベスト保険の補償範囲と具体的な事例
- アスベスト除去費用の相場と保険適用のシミュレーション
- 2025年時点のアスベスト関連法規制と罰則
- 従業員の健康被害リスクと労災保険の活用方法
目次
【解体工事保険の関連記事】
「解体工事の作業対象である建物そのものは、多くの保険で補償の対象外になる」
実は、解体事業者が加入する賠償責任保険には、このように補償が適用されない「免責事項」がいくつも定められています。
このルールを知らないまま万が一の事態が起きれば、損害が自己負担となり、会社の経営に大きな影響を与えることも 解体工事では、事前調査で把握できなかった地中埋設物が、追加費用や工期遅延の原因となることがあります。
実際、地中埋設物をめぐる裁判では、除去費用約830万円の支払いが認められた事例(福岡地裁小倉支判平成21年7月14日)もあり、そのリスクは決して小さくありません。
出典:RETIO「判例」 「解体工事の騒音クレームは、保険で対応できるはずだ」
もし、そう考えているのであれば注意が必要です。
結論からいうと、解体工事にともなう騒音・振動・粉塵といった近隣トラブルは、原則として保険の適用対象外です。
そう聞くと、「一体何のための保険なのか」と疑問に思われるかもしれません。
この記事
解体工事の保険と免責|「保険が効かない」5つのケースと対策

解体工事の地中埋設物リスク|保険適用の条件と正しい備え方【事例付き】

解体工事の保険で騒音・振動は補償されない?免責の理由と本当に必要な備えとは
アスベスト関連の損害は一般的な工事保険では補償されない

ほとんどの事業者が加入している「工事保険」や「賠償責任保険」では、アスベスト関連の損害は補償の対象外となっています。
これらの保険の約款をよく読むと、「アスベスト、PCB、ダイオキシン等の有害物質による損害については、保険金をお支払いしません」という趣旨の免責条項が、ほぼ必ず書かれています。
つまり、普段加入している保険が、アスベスト関連の事故では使えないのです。
解体工事保険の免責事項の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

解体工事の保険と免責|「保険が効かない」5つのケースと対策
「解体工事の作業対象である建物そのものは、多くの保険で補償の対象外になる」 実は、解体事業者が加入する賠償責任保険には、このように補償が適用されない「免責事項」がいくつも定められています。 このルールを知らないまま万が一の事態が起きれば、損害が自己負担となり、会社の経営に大きな影響を与えることも
なぜ、これほど大きなリスクであるはずのアスベストが、一般的な保険では補償されないのでしょうか。
主な理由は2つあります。
①損害の予測が難しいから
アスベストによる健康被害は、数十年という長い潜伏期間を経て発症することがあります。
いつ、誰に、どのくらいの規模の被害が出るのかを予測するのが極めて難しいため、保険会社はリスクを計算できず、補償の対象から外しているのです。
②汚染の範囲が広がりやすいから
アスベストは極めて細かい繊維のため、一度飛散すると広範囲に拡散し、除去(原状回復)にも莫大な費用がかかります。
この損害の大きさが、通常の保険でカバーできる範囲を大きく超えてしまうことも理由の一つです。
実は、解体工事に潜むアスベストのリスクは、年々、より大きなものになっています。
そのため、元請業者様には、協力会社の安全管理体制も含めて、より一層の注意が求められるようになっています。
では、アスベストリスクは具体的にどれくらい大きいのでしょうか。
アスベストリスクの大きさを知る

一般的な保険では補償されないアスベストですが、そのリスクは決して小さくありません。
実際の費用や罰則を見ていきましょう。
アスベスト除去費用の相場
アスベストが発見された場合、適切な除去作業が必要になります。
その費用は、アスベストの種類や面積、作業レベルによって大きく変わります。
| 作業レベル | 対象 | 単価(1㎡あたり) | 費用の目安 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 吹付けアスベスト | 1.5万円〜8.5万円 | 100㎡で150万円〜850万円 |
| レベル2 | アスベスト含有断熱材・保温材(配管、ボイラー) | 1万円〜3万円 | 50㎡で50万円〜150万円 |
| レベル3 | アスベスト含有建材(スレート板、サイディング) | 0.2万円〜0.8万円 | 200㎡で40万円〜160万円 |
レベル1(吹付けアスベスト)は最も危険度が高く、養生や集塵機の設置など、厳重な飛散防止対策が必要なため、費用は高額になります。
レベル2(アスベスト含有断熱材・保温材)は、配管の保温材やボイラー周りの断熱材などの除去が該当します。
レベル3(アスベスト含有建材)は、スレート板やサイディングなど、固形化されたアスベスト含有建材の除去です。
アスベスト調査費用
除去の前には、必ず事前調査が必要です。
建材調査(分析費用):1検体あたり2万円〜5万円
建材を採取し、アスベストの有無を分析します。
複数箇所の調査が必要な場合、総額で10万円から30万円程度になることもあります。
気中濃度測定:1箇所あたり3万円〜10万円
作業中や作業後に、空気中のアスベスト濃度を測定します。
複数回の測定が必要な場合、総額で20万円から50万円程度が必要です。
2025年時点のアスベスト関連法規制と罰則
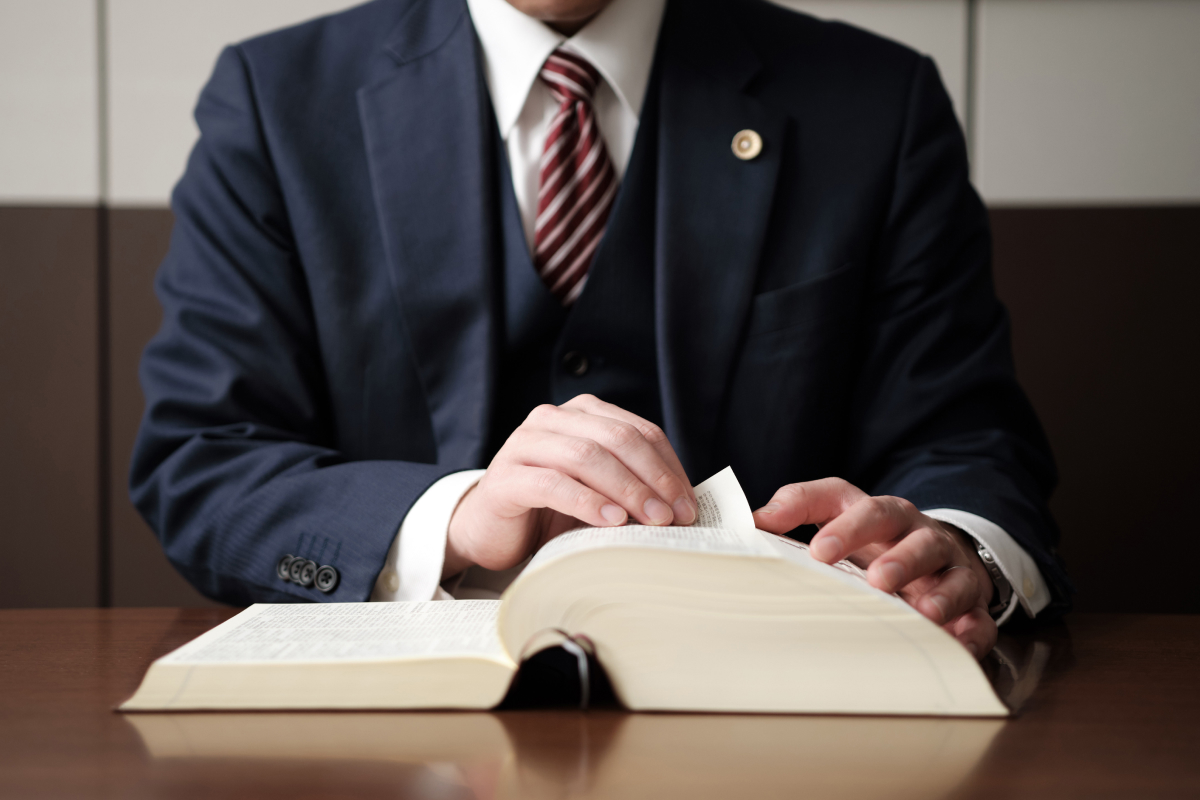
アスベスト対策は法律で厳しく規制されており、違反した場合は厳しい罰則が科されます。
労働安全衛生法と石綿障害予防規則
労働者の安全と健康を守るための法律です。
アスベスト作業については、石綿障害予防規則(石綿則)で具体的な対策が定められています。
- 事前調査の義務(石綿則第3条)
- 作業計画の作成(石綿則第4条)
- 作業主任者の選任(石綿則第19条)
- 特別教育の実施(石綿則第27条)
- 作業場所の隔離と集塵・排気装置の設置(石綿則第6条・第13条)
労働安全衛生法違反として、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)が科される可能性があります。
大気汚染防止法
アスベストの大気中への飛散を防止するための法律です。
2021年4月の改正により、規制が大幅に強化されました。
- すべての建築物の解体・改修工事における事前調査の義務化(第18条の15)
- 事前調査結果の都道府県知事等への報告義務(第18条の17)
- 作業基準の遵守(第18条の19)
- 作業結果の発注者への報告と記録の保存(3年間)
- 作業基準違反:3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(第34条)
- 事前調査結果の報告義務違反:30万円以下の罰金(第35条)
- 虚偽報告:30万円以下の罰金(第35条)
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律では、アスベスト含有建材の適正な分別解体と処理が義務付けられています。
アスベスト飛散事故の損害額

もしアスベストが飛散してしまった場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
健康診断費用:被害者一人あたり5万円〜20万円
飛散事故後、近隣住民への健康診断実施が必要になります。
30世帯で実施した場合、150万円から600万円が必要です。
慰謝料・見舞金:一世帯あたり10万円〜50万円
精神的苦痛や生活への影響に対する補償です。
30世帯で300万円から1,500万円が必要です。
除染費用:周辺環境の浄化に500万円〜3,000万円
周辺建物や土地に付着したアスベストの除去には、広範囲の作業が必要で、高額になります。
このように、アスベストに関わるリスクは、除去費用だけで数百万円、飛散事故が起これば数千万円に及びます。
さらに、法令違反には懲役刑や罰金も科されます。
では、これほど大きなリスクに、どのように備えればよいのでしょうか。
アスベストにはアスベスト専用の保険・保証制度で備える
一般的な工事保険ではアスベストは補償されませんが、実はアスベストリスクに特化した保険や保証制度が存在します。
アスベストに関連する事業リスクは、大きく分けて以下の3つに分類でき、それぞれに対応する保険や保証制度があります。
- 第三者への賠償(飛散事故)
- 想定外のコスト増(追加の除去費用)
- 従業員の健康被害(労災)
一つずつ、具体的に見ていきましょう。
①第三者賠償・環境汚染のリスク:AIG損害保険「アスベスト飛散事故補償特約」

もし、解体工事中にアスベストが飛散し、近隣住民の方の健康や周辺の建物に影響を与えてしまった場合、その賠償責任は非常に大きくなる可能性があります。
特に、元請事業者は下請けが起こした事故であっても、その責任を免れることはできません。
この第三者への賠償リスクに備えるために現在利用できる主な手段が、AIG損害保険の事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)の「アスベスト飛散事故補償特約」です。
これは、一般的な賠償責任保険では対象外だったアスベスト飛散事故を正面から補償する特約です。
補償される費用
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 石綿損害拡大防止費用 | 飛散を食い止めるための養生シート補修など、緊急措置にかかった費用 |
| 石綿損害見舞費用 | 近隣の住民や事業者への見舞金 |
| 石綿除去等費用 | 近隣の建物や物品に付着したアスベストの除染や廃棄にかかる費用 |
この特約を付けておくことで、これまで自社で対応するしかなかった飛散事故後の初動対応から、周辺への補償までカバーできるようになります。
②想定外のアスベスト除去費用:損害保険ジャパン「アスベストコストキャップ保証」

この制度は、当初の想定よりもアスベストの量が多く、除去費用が追加でかかってしまう、という事態に備えるための保証制度です。
解体工事では、設計図書には記載がなかった場所から、新たにアスベストが見つかるケースも珍しくありません。
そうなると、工期の延長や追加の除去費用が発生し、元請業者様や施主様にとって大きな負担となってしまいます。
こうした「想定外のアスベスト出現によるコスト増」というリスクに備える国内初のサービスが、損害保険ジャパンと環境コンサルティング会社のフィールド・パートナーズが共同開発した「アスベストコストキャップ保証」です。
これは保険というより「保証サービス」に近い仕組みで、事前に専門家によるリスク評価を受けた上で、万が一、想定を超えるアスベスト除去費用が発生した場合でも、その超過分が保証されます。
これにより、事業者は「これ以上の費用はかからない」という上限額を確定させた上で、安心して工事を進めることができます。
プロジェクトの予算オーバーという直接的な経営リスクを防ぐ上で、非常に役立つ制度です。
③従業員のアスベスト健康被害:政府の「労災保険」と民間の「上乗せ保険」

アスベストを扱う作業は、作業員の健康にとって大きなリスクを伴います。
そのため、従業員や一人親方への労災対策は、事業者にとって大切な責務です。
このリスクに対する基本の備えは、国が管掌する「労働者災害補償保険(労災保険)」です。
従業員が業務を原因としてアスベスト関連の病気になった場合、治療費や休業中の給与の一部が労災保険から支払われます。
しかし、国の労災保険でカバーされるのは、あくまで基本的な補償です。
万が一、会社の安全管理体制に不備があったとされ、従業員やその遺族から慰謝料など高額な損害賠償を請求された場合、その費用を労災保険だけでカバーするのは難しいでしょう。
その不足分を補う役割を果たすのが、民間の「労災上乗せ保険(業務災害総合保険)」です。
この2つの保険を組み合わせることで、従業員への補償と会社の賠償リスクの両方に、より手厚く備えることができるのです。
従業員と自分を守る「労災保険」活用の知識
3つのリスクのうち、特に経営者や従業員の人生に直接関わってくるのが、この「労災保険」の問題です。
国の制度だからと安心するのではなく、その仕組みと、どこまでカバーされるのかを正しく理解しておくことが大切です。
国の「労災保険」で補償されること(治療費・休業補償)

国の「労災保険」は、労働者を守るための強力なセーフティーネットです。
業務中や通勤中のケガはもちろん、アスベスト関連の疾病のように、業務が原因で発症した病気も補償の対象となります。
主な補償内容
| 給付の種類 | 内容 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 治療にかかる費用は、原則として全額が給付されます。健康保険のような自己負担はありません。 |
| 休業(補償)給付 | 療養のために働けず、給与を受けられない日が4日以上続く場合、4日目から休業前の給与の約8割に相当する額が支給されます。 |
| 障害(補償)給付・遺族(補償)給付 | 後遺障害が残った場合や、死亡に至った場合には、その後の生活を支えるための年金や一時金が給付されます。 |
このように、従業員に対する補償は手厚いものですが、注意すべき点があります。
この制度は、あくまで「労働者」を対象としています。
つまり、会社の経営者や役員、そして一人親方といった方々は、原則としてこの補償の対象外なのです。
これらの立場の方が業務中の災害から身を守るには、「特別加入制度」に自ら申請し、加入しておく必要があります。
もしこの手続きを忘れていると、万が一の際に公的な補償が受けられず、治療費や休業中の収入もすべて自己負担になってしまう可能性があります。
国の補償だけでは足りない!慰謝料などに備える「労災上乗せ保険」

国の労災保険が手厚いセーフティーネットであることは事実です。
しかし、それだけでは会社が負うべき責任のすべてをカバーできるわけではない、という点も知っておく必要があります。
もし、労災事故の原因が会社の「安全配慮義務違反」にあると判断された場合、被災した従業員やその遺族から、民事上の損害賠償を請求される可能性があります。
民法第415条(債務不履行による損害賠償)では、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができると定められています。
国の労災保険から給付されるのは、治療費や休業補償といった実費補填が中心です。
精神的苦痛に対する「慰謝料」や、事故がなければ将来得られたはずの収入である「逸失利益」といった、労災保険の枠を超える部分については、会社が直接支払う責任を負います。
- 慰謝料
健康被害の程度に応じて500万円〜3,000万円石綿肺、中皮腫などの重篤な疾病の場合、高額な慰謝料が認められます。 - 逸失利益
将来得られたはずの収入若年層の労働者が重度の障害を負った場合や死亡した場合、数千万円から1億円を超えることもあります。 - 弁護士費用・訴訟費用
数百万円 民事訴訟になった場合、弁護士費用や訴訟費用も必要です。
過去の判例では、数千万円から1億円を超える賠償命令が出ることも珍しくありません。
この、会社の存続にも影響を与えかねない賠償リスクに備えるのが、民間の「労災上乗せ保険(業務災害総合保険)」に含まれる「使用者賠償責任補償」なのです。
これに加入しておくことで、万が一、高額な損害賠償を命じられた場合でも、その賠償金を保険でカバーできます。
従業員を守り、そして会社そのものを守るためにも、「国の労災保険」と「民間の上乗せ保険」は、セットで加入しておくことをお勧めします。

【建設業向け】使用者賠償責任保険で高額リスク回避!労災だけでは足りない理由と注意点
建設現場では、高所作業や重機の使用など危険が伴う場面が多くあります。 もし事故が起きて従業員の方が大けがをした場合、企業(使用者)には高額な賠償責任が問われる可能性があります。 労災保険にはすでに加入している企業がほとんどだと思いますが、実はそれだけではカバーしきれないリスクがあることをご存じで
アスベスト問題を機に、自社の工事保険を総点検しましょう

ここまで、アスベストという特殊なリスクへの向き合い方を解説してきました。
しかし、このアスベストの問題は、自社のリスク管理全体を見直す良いきっかけになるかもしれません。
これを機に、アスベスト以外のリスクも含めて、現在加入している工事保険が本当に会社の状況に合っているのか、一度見直してみてはいかがでしょうか。
自社のリスクを洗い出し、現在の保険の「穴」を見つける
まずは、お手元にある保険証券を広げ、内容を隅々まで確認することから始めてみましょう。
「石綿」の文字を探すのはもちろんですが、それ以外にも見落としがちなポイントがいくつかあります。
地盤沈下や振動による損害
解体工事に伴う掘削や振動が原因で、隣の建物にひびが入った…。
こうしたケースは、標準的な賠償責任保険では「免責」とされ、補償されないことが少なくありません。
管理下の財物への損害
工事中、お客様から一時的に預かった家財や、借りている重機を誤って壊してしまった場合も、通常の賠償保険ではカバーされません。
補償限度額は十分か
「対人賠償1億円」で契約していても、大きな事故が起これば、その額では全く足りない可能性があります。
現在の事業規模や、元請けから要求される基準に照らして、保険金額が妥当かどうかを再評価する必要があります。
これらの項目が、ご自身の保険でどのように扱われているかを確認するだけでも、潜んでいるリスクが見えてくるかもしれません。
解体工事の保険見直しは以下の記事でも解説しています。

解体工事の保険は「見直し」で大きく変わる!保険料節約と補償を手厚くする方法
解体工事は、数ある建設工事の中でも、特に事故のリスクが高いと言われています。 建物を取り壊していくという作業には、どうしても予測しきれない危うさや、隣接する建物への影響なども考えなくてはいけないからです。 解体工事を営む経営者の方や、現場の安全管理を担う責任者の皆様は、「うちの会社の保険、本当に
保険料をうまく抑える「団体割引」の活用
「補償を手厚くすれば、当然、保険料も高くなる」。
そうお考えになるのはもっともです。
しかし、保険料は契約の仕方一つで大きく変わることがあります。
その代表例が「団体割引」の活用です。
多くの建設業組合や商工会議所では、会員向けに団体契約の保険制度を用意しています。
こうした制度を利用すると、個別に契約するよりも保険料が大幅に割安になるケースが多く、条件次第では30%から、時には80%近くも保険料を抑えられることがあります。
もし現在、保険会社と直接、個別に契約しているのであれば、一度、所属している組合などの制度を確認してみることをお勧めします。
補償内容はそのままに、固定費である保険料を削減できるかもしれません。
まとめ:アスベストリスクに適切に備えよう
解体工事におけるアスベストのリスクは、一般的な工事保険では補償されない特殊な問題です。
- 一般的な工事保険ではアスベストは免責
多くの工事保険では、アスベストによる損害は補償の対象外です。 - 除去費用は数百万円規模
レベルによって1㎡あたり0.2万円〜8.5万円、飛散事故が起これば数千万円に及びます。 - 3大リスクに専門保険で備える
「第三者賠償」「コスト増」「労災」には、それぞれ専門の保険・保証制度を組み合わせる必要があります。 - 労災上乗せ保険が不可欠
国の労災だけでは不十分で、高額賠償(慰謝料や逸失利益で数千万円〜1億円超)に備える民間保険が必要です。
これらの対策を、自社の事業内容に合わせて複合的に構築していくことが大切です。
もし、「うちの会社には、どの保険の組み合わせがベストなのか」「保険証券のどこを確認すればいいのか」といった疑問をお持ちでしたら、建設・解体業の保険に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
専門家であれば、自社のリスクを客観的に分析し、本当に必要な補償と削っても問題ない補償を仕分けし、最適な組み合わせを提案してくれます。
私たちマルエイソリューションでは、建設・解体業の保険分野でこれまで多くのお客様のリスク対策をお手伝いしてきました。
ご相談・お見積もりは無料です。全国どこからでもオンラインでお気軽にお問い合わせください。



